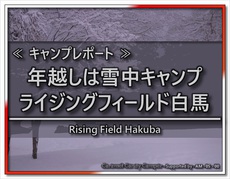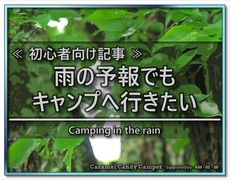初心者の為のテントの話
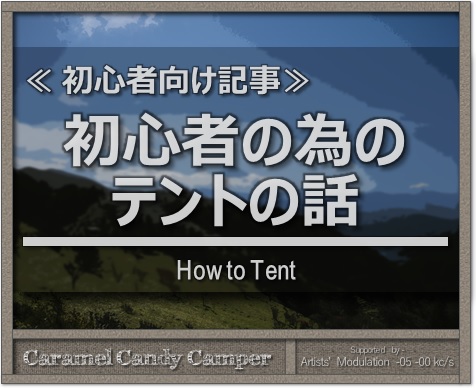
こんにちは、Hagarieです。
今回、キャンプで最重要となってくるテントの話しをしていきたいと思います。
このBlogを立ち上げて間もない頃、一回テントについて記事を書いたものの、テントの種類とか一切説明していない雑な記事だったので、今回その記事のやり直しをします。
2018/02/23キャンプと言ったらテント。テントと言ったらキャンプ。今回はテントについて記事を書いてみようと思う。キャンプをするにあたり大抵の場合、テントが無いと始まらない。最近ではテントを使わずタープやハンモックで一夜を過ごす人達も多くなってきたけど、ステレオタイプな視点から言えば、やはりキャン…
懐かしいものです。と思ったけどまだ2ヶ月前なのね。
という事でまず始めにテントの構造を説明していきたいと思います。
テントの構造
まずはテントの構造とその役割、名称を説明していきます。
テントは以下の4種類の部品から出来ています。
■テント本体となる「インナーテント」
■インナーテントを支える「ポール」
■雨や風から保護する「フライシート」
■それらを地面に固定する「ペグ」


もちろん例外も少なくありませんが、大体のテントはこれらの4種類の部品から成り立っています。次にそれらについて説明していきます。
インナーテント
インナーテントはテントの中心、居住スペースとなる部分です。組み立て前は袋状の布ですがポールによって立体構造となり居住空間となります。一般的には通気性を持たせるため床部を除き撥水性のみを持たせ防水性はありませんが、防水性を持たせフライシートを省いた"シングルウォール"と呼ばれるモデルもあります。逆に床部分以外が全てをメッシュ生地の通気性に優れたモデルなんかもあります。
ポール
ポールはインナーテントを立体化させる為のフレーム、または柱となる部分です。インナーテントとの接続の仕方も色々ありますが、主流なのは2種類あって、インナーテント側にフックが付いていて、それをポールに引っ掛けて接続する"吊り下げ式"と、インナーテントの生地の一部が筒状構造になっており、そこにポールを通して接続する"スリーブ式"があります。慣れれば設営時間に殆ど変わりはありませんが、吊り下げ式の方が適当にやっても接続出来るので私は好きです。
フライシート
インナーテントを覆い、屋根や外壁となる部分です。生地は防水・撥水加工され雨風や汚れを防ぎます。前述した通りフライシートの無いモデルは"シングルウォール"と呼ばれ、逆にフライシートのあるモデルは"ダブルウォール"と呼ばれます。多くのモデルではテントの入り口付近のフライシートとインナーテントの隙間を広く確保し"前室"としています。前室は雨風を防げる為、土間の様な扱いが出来、天候が悪い時はここで調理等も出来ます。前室にストレス無く居られるスペースを持つテントは"ツールーム式"と呼ばれます。また後ろ側にも同様の構造"後室"があるモデルもあります。
ペグ
フライシートを含むテント全体を地面に固定する部品です。地面の状況により使い分けするのをオススメします。(→関連:ペグについて)
テントの用途別の分類
テントの用途別に以下の3種類に大別できます。
■軽量で持ち運び前提の山岳用テント
■山岳テントよりはやや大きいツーリングテント
■車で運ぶこと前提の一般的なテント
多くの場合、軽さや収納性、価格設定は、
山岳テント >>>>> ツーリングテント >> 一般的なテント
となります。
そういった目線で見ると山岳用テントが優れていると思われますが、山岳でもツーリングでも無い普通のオートキャンプ用途であればそれらを選ぶ必要も無く、逆に価格が高く気安く扱えなかったり、コンパクトさを求めるあまり居住スペースが狭かったり、組み立てや撤収が複雑で面倒くさかったり、収納袋がキツキツだったりとデメリットも少なくありません。まずは用途に合ったテントを選びましょう。

テントの形状別の分類
テントの形状別に幾つかの種類よって大別できます。
クロスフレーム型ドームテント

2本のポールを反らせクロスさせることでテントを広げ形作ります。構造の単純さから組み立て易く撤収も比較的簡単です。また、その丸めのフォルムは風を受け流す事が出来ます。初心者から上級者まで愛用者が多い現在一番主流のテント形状です。
ジオデシック型ドームテント

クロスフレーム型ドームテントの派生で、複数のポールを複雑に組み合わせることで、軽さと組み立て易さと引き換えに強度と居住性を向上させたモデルです。
ロッジ型テント

ドーム型とは違い、ただフレームを組んで形作ります。設計自体は非常に古く、ベテランキャンパーさんは"鉄骨"なんて呼び方をしますね。天井が高く居住性も非常に高いです。多くのモデルはフラップを大きく設け夏でも快適に過ごすことが出来、薪ストーブのインストールも容易で冬のキャンプにも向いています。見た目の割りに組み立ても簡単で大きなロッジ型でも一人で組み立てが可能です。ただ、設営面積がかなり広く必要なのと、その背の高い構造上風に弱いです。また強度が必要となる為フレームが太く、それによりとにかく重く、携行性と収納性がとても低いです。
Aフレーム型テント

Hフレーム型とも呼ばれることがあります、ロッジ型の派生ですね。いかにもテントな形をしていますが、やはり設計が古く現在ではメリットが少ないようです。当時としてはロッジ型よりも軽くコンパクトで組み立ても簡単、風にも強いとメリットも多かったのですが...(→関連:ムーンライトテントについて)
ティピー型モノポールテント

代表的なモノポールテントです。今まで紹介したテントとは違いこのテントはポールがフレームの働きをしない"非自立型"テントです。モノポールテントは、ワンポールテントなんて呼ばれ方もしますね。このタイプのテントはポールが柱の役割だけでフレームの役割はテンションを掛けた張り綱が果たします。ポールが少ない分軽く、組み立ても簡単とメリットも多いですが、その構造により設営面積が広く必要だったり地面の形状や硬さによりテントの強度などが左右される等のデメリットもあります。
このティピー型モノポールテントはさらに全体が屋根というか壁が傾斜しているためフラップを設置出来ないので換気性が低く、出入り口にも前室やフラップが無く、雨の際には非常に雨水が侵入し易いデメリットがあります。しかし最近では、壁面に上手いことベンチレーションを付けたモデルや、出入口にフラップがあるモデル、ソロ用では前室があるモデルも増えてきています。
ベル型モノポールテント

ティピー型モノポールテントの派生型です。ティピー型は構造上、雨侵入のリスクがある為フラップが無く、換気性が低いという問題点がありましたが、ベル型ではテントの淵部分がサイドウォールとして立ち上がっており、そこに換気用のフラップが設置されています。通常のティピー型に比べ換気能力が高く雨にも強い為、日本の風土にはベル型のほうが合っています。しかし、まだモデルが少なくソロ用テントでは存在しないと思います。
トンネル型テント

かまぼこテントなんて呼ばれ方もする非自立型テントです。ポールをアーチ状に曲げ、それを生地と張り縄により保持する構造です。設計が新しく、まだモデルは少ないですがロッジ型テント並みの広さが確保出来るのに、ポールの数が少ないので軽量という夢の様なテントです。しかしポール素材が悪いと簡単に破損してしまい信頼性の高いポール素材のモノは価格が高いというデメリットがあります。まだ時代が追いつけていない印象です。
初心者にオススメのテント
ダブルウォールの吊り下げ式クロスフレームドーム型テントがオススメです。
クロノスドーム

ダブルウォールで吊り下げ式クロスフレームドーム型テント←これ以上の説明は要らないと思いますが、その中でもクロノスドームは安心のモンベルですしオススメ出来ます。私の愛用しているムーンライトテントをディスった店員もクロノスは褒めてましたし...。
クロノスキャビン

前述したクロノスドームの前室を広くしたモデルですね。
最後に
キャンプにおいてテントとは家。
テントを使わずに車中泊や、コテージ泊をする人も少なくありませんが、
私からすると、それはキャンプでは無く少しジャンルが違うように感じます。
考えを押し付ける訳ではありませんが、
キャンプではテントを設営し、そこで寝るというのが最大の醍醐味だと思います。
また酷いテントは想像を超えて酷い場合があります。
ですのでキャンプを台無しにしない為にもテントを買う時はよく吟味し、後悔が無いようにしっかりと選んでください。
以上、宜しくお願いします。
初心者の為の寝袋の話
広告